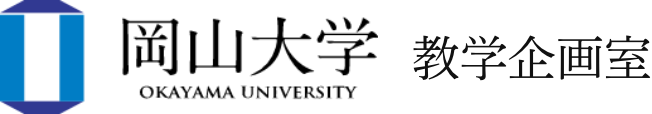【開催報告】桃太郎フォーラム2025
桃太郎フォーラム2025を開催
教学企画室は、2025年9月29日に本学津島キャンパス一般教育棟A棟2階A21教室にて桃太郎フォーラム2025を開催しました。参加者は学内者、学外者を合わせて約100名でした。

第28回目の開催となる今回のフォーラムは、学外からも登壇者をお招きし、テーマを「今こそ、学生が思考するキャンパスをつくる」として、学生が思考することに焦点を当てたシンポジウムとしました。菅誠治理事(教学担当)・上席副学長の開会挨拶に続き、文部科学省高等教育局大学振興課地域大学振興室長の石川雅史氏から来賓挨拶をいただきました。
次に、田中岳副学長(教育・入試改革担当)から、「感じる」「思う」「考える」の順次性、「個人思考-集団思考」軸と「発想・対話・創出-知識・伝授・習熟」軸に加え、「正課-正課外」軸による枠組みについて説明がありました。その後の事例報告は以下のようなものでした。

小川慎二郎氏(早稲田大学高等学院)は、早稲田大学高等学院における探究プログラム及び探究活動 に関する話題提供を行いました。探究活動の具体例や生徒のモチベーションを高める工夫、生徒の自主的・主体的活動への支援制度について、長く物理教育に携わってきた視点から報告を行いました。


続いて、本学が2025年度から展開する課題探究科目「知の探研」について、小山敏広氏(学術研究院医歯薬学域)、田尾周一郎氏(学術研究院共通教育・グローバル領域)から報告がありました。授業担当教員及び課題探究班長の視点から、岡山大学における課題探究科目「知の探研」開発の経緯、学部を超えた学生の混在に加え学生と教員や専門の異なる教員同士といった「混ぜる・混ざる」を意識した授業設計と実践例、学生アンケート等からみえた成果と今後の展望についての話題提供を行いました。
次に、本学の大学院共通科目の一環として、環境生命自然科学研究科が提供する海外研修プログラム(OU-TACT; Okayama University – National Taiwan Normal University Communicative Training Program for Master Students)に関する話題提供がありました。大学院生として本プログラムに参加した森紀華氏(ヘルスシステム統合科学研究科博士前期課程)は、台湾の先端企業や研究施設、国立台湾師範大学大学院生等から得られた示唆について述べ、今後の自身の研究活動にどうつながったのかを報告しました。

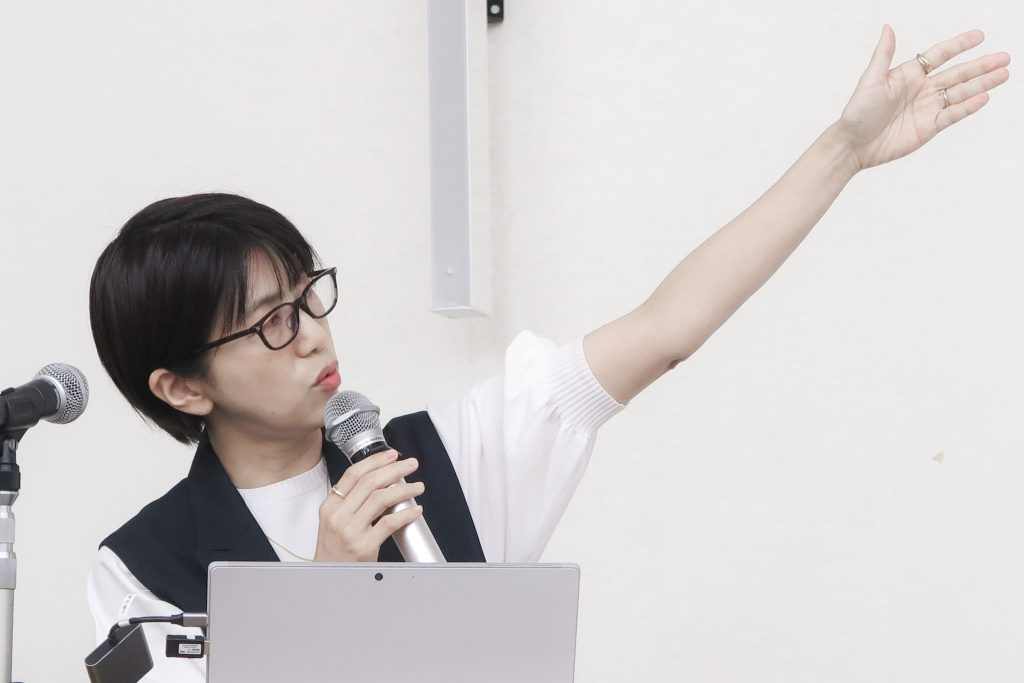
最後に、岩﨑千晶氏(関西大学)は、ラーニングコモンズのデザインと学生の学びに関する話題提供を行いました。具体的な事例として、関西大学におけるラーニングコモンズ 活用方法、ラーニングコモンズにおける正課・正課外活動での思考について紹介しました。それらを受け、学生が思考することに向けた学習支援のあり方や、学生が思考するラーニングコモンズをつくる際の論点について学習環境デザインの視点から整理し、報告を行いました。
パネルディスカッションでは、福留東土氏(東京大学)が指定討論として、思考することをめぐる身体性、相対性、協働性という3つの基本的視点を示しました。続けて、「思考するということについて、教育における知識のあり方を再考してみる必要があるのではないか」、「混ぜる・混ざることの先に、どのようなものを期待するのか」といったコメントを提示しました。その後、事例報告の登壇者と石川氏がパネリストとして登壇し、和賀崇氏(学術研究院共通教育・グローバル領域)がモデレーターとなり、学生が思考することについて活発な議論が行われました。そこでは、探究活動における「個人」と「チーム」とのバランスをいかにハンドリングするか、思考につながる興味関心をいかに高めるか、手段としての「混ぜる・混ざる」ことが教育に何をもたらすのかなど、高校や大学といった制度の枠組みを超えて、学生が思考するとき何が起きているのかについての議論が展開されました。また、会場の参加者からも活発に質問がなされ、複数キャンパスをまたがる授業運営の工夫など、より具体的な内容に踏み込むことができました。




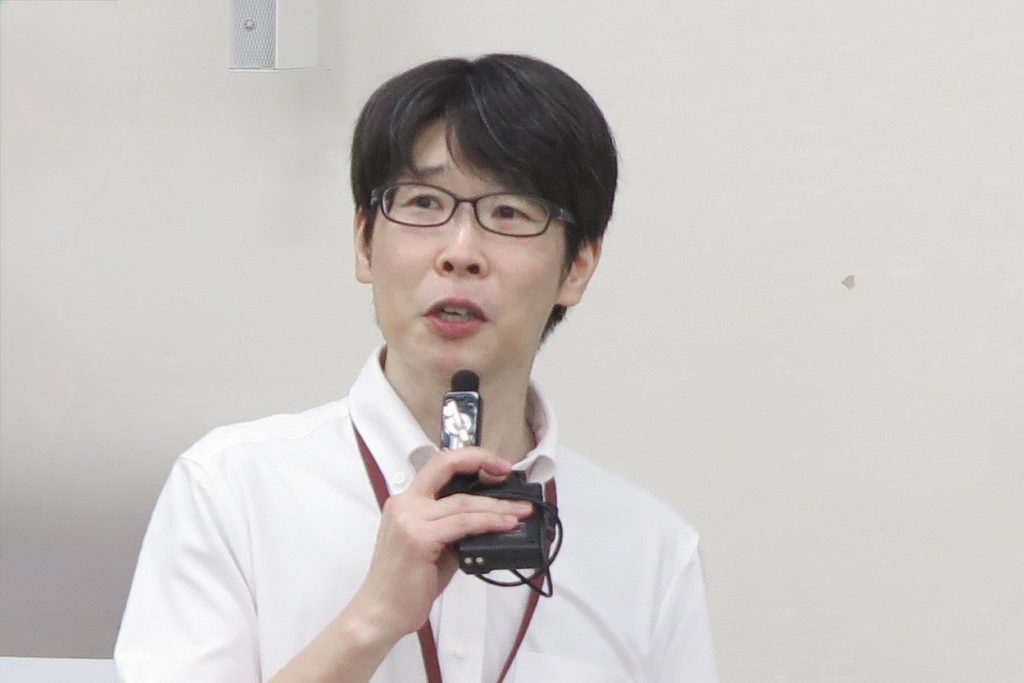
フォーラムの最後には、三村由香里理事(企画・評価・総務担当)より閉会挨拶があり、盛会のうちに終了しました。

参加者アンケート(19件/回収率17.1%)においては、90%以上の参加者が「満足」「やや満足」と回答しています。また、事例報告についても、90%程度の参加者が「とても役立つ」「役立つ」「やや役立つ」と回答しており、今後の活動の参考になる機会であったことが分かりました。自由記述には、「多様な分野の学生が混在しながら新たな知を生み出すということの重要性が良く理解できた。」「多様な事例を一堂に聞くことができ、有意義でした。」等の感想が寄せられました。
なお、本フォーラムを広報するにあたり、広島大学高等教育研究開発センター「新着情報通知サービス」、愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室「ぼっちゃんメーリングリスト」を利用させていただきました。末筆ながら、ここに記して感謝申し上げます。
(参考情報)